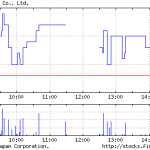1月にマイナス金利が導入されてから約2か月が経過しました。
自分は企業内で経理を行っているのですが、マイナス金利が導入されたことで
財務諸表の数字にいくつか影響があるので取り上げてみたいと思います。
-
財務諸表に影響を与えるもの
① 退職給付債務の算定の際に利用する割引率
② 資産除去債務の算定の際に利用する割引率
③ 減損会計において使用価値を算定する際に利用する割引率
の3つぐらいだと思います。
なお、財務諸表に影響を与えないが経営に大きく影響を与えるものとしてはM&Aが挙げられます。
この4つに影響を与える理由は割引現在価値(DCF)という考え方により
将来キャッシュフロー(将来もらえる予定の現金)を現在の価値と比較して計算するときに
使用する割引率に金利が影響を与えるためです。
-
割引現在価値について
今日の100万円と1年後の100万円は同じかどうかという問題から来ています。
もし金利が10%の銀行があったとして今日100万円もらえれば
1年後には100万円+100万円×10%=110万円になります。
となると今日の100万円と1年後の100万円を比べると
明らかに今日の100万円のほうが価値があります(銀行に預けておけば1年後には110万円になるため)。
ではこのとき1年後の100万円は現在いくらであればイコールとなるのかを考えてみます。
100万円を銀行に預ければ1年後110万円と1.1倍(100%+10%)になってきていますので計算式は
100万円×1.1=110万円となります。
であるならば110万円の部分に100万円をいれて計算すると
00万円×1.1=100万円
00万円=100万円÷1.1
00万円=約90.9万円となります。
これで今の約90.9万円と1年後の100万円が同じ価値であるということになります。
ここで重要なのは金利が変わると現在の価値が大きく変わることです。
金利がー10%として考えた場合
100万円÷0.9=約111.1万円となり
現在の111.1万円と1年後の100万円が同じ価値になるという計算になります。
金利がー10%のときと10%のときで比較すると
111.1万円ー90.9万円=20.2万円
の差が出てきます。
例題としてわかりやすくするために10%と-10%という大きな金利で計算しましたが、
金利が割引現在価値という手法に大きく影響を与えることを認識していただければ幸いです。
-
①退職給付債務について
この引当金の計算に割引現在価値の考え方が取り入れられています。
具体的には
従業員のAさんが来年退職することになっていて、退職金として100万円支払う予定だったとします。
このとき企業の貸借対照表の負債の部には100万円の割引現在価値の金額が計上されます。
昨日の例で説明しますと
金利が10%のときは約90.9万円が計上され
金利がー10%だと約111.1万円が計上されることになります。
つまり金利が下がると引当金の額が大きくなるため負債の額も比例して大きくなってしまいます。
金利の変更で引当金に繰り入れする必要が出てくるため資本の額が少なくなり負債の額が増えることになります。
(金利の変更により退職給付債務の計算が変わるときは、差額を数理計算上の差異という名目で
一定年数にわたって費用化するため損益に与える金額は比較的小さいと思います)。
株式のトレードでROE(株主資本利益率)やPBR(純資産倍率)、一株当たり純資産額を
ファクターとして利用し銘柄を選択している方もいらっしゃると思いますが、
金利が変わったことによりこれらの数字が変わってしまうため
今までトレードしていた銘柄から別の銘柄へ組み替える必要が出てくるかもしれません。
そのため短期投資家なら空売りチャンスかもしれません。
なお退職給付債務の金額が変わりやすいのは
① 従業員が多い会社
② 退職給付債務が多い会社
③ 高い割引率で計算していた会社
④ 給料が多い会社
が挙げられると思います。
-
②資産除去債務について
将来固定資産を売却や解体または撤退(引っ越し)するときにかかる費用を
債務として認識しようとする考え方です。
将来の費用ということでここでも割引現在価値の考え方が出てきます。
なお出鼻をくじくようで申し訳ありませんが、資産除去債務の計算は、退職給付債務の計算と違い
金利の変更があっても資産除去債務を計上した時から計算の見直しをしないためすぐには財務諸表に影響はありません。
ただし解体などの費用の見積もりを変更した時は、そのときの金利を使用するため影響が出てきます。
割引現在価値の計算方法は退職給付債務と同じため株式トレードにどういった影響が出てくるのかを考えます。
資産除去債務の問題が出てくるのは固定資産を買ったり借りたりすることが多い小売業や
大規模な工場を必要とする自動車、電力、化学などの業種です。
まず小売業では店舗を借りて運営していると思いますが、店舗を借りた時に
原状回復費用を見込んで割引現在価値考え方を適用して建物などの取得原価とします。
そしてその取得原価をもとに減価償却費を計算していきます。
そのため金利が低くなると原状回復費用が多く計算されるため減価償却費が多くなり利益を圧迫することになります。
今後全国展開を考えて店舗数を増やそうとしている小売業にとっては無視できない影響が出てくると考えられます。
次に大規模な工場を必要とする業種の場合
工場が大きいあまり原状回復費用が高額になりやすいことや
特に原子力発電などは土壌汚染を引き起こしたりする可能性があるため、
さらに資産除去債務が大きくなりやすいと考えられます。
また工場の減価償却費は基本的に原価に計上されるため原価率が上昇することになります。
(なお小売業の場合は販売費及び一般管理費に計上されることが多いです)
そのため大規模な工場などを作ろうとしている企業にも影響が出てきます。
長期トレードを考えた場合、金利が下がった時は小売業や大規模な工場を作ろうとしている企業は
利益が圧迫されるため株価が上昇しづらくなるかもしれません。
ちなみにIFRSが適用されると金利を毎年見直す必要が出てくるため
影響がさらに大きくなります。
-
③減損会計について
回収可能な額まで資産の評価額を引き下げる会計処理をいいます。
この回収可能な額には2つあり①今売却した時に回収できる金額②将来に渡って使用していくこと回収できる金額です。
たとえば工場を買ったはいいものの、工場を使用して作る商品が今後売れる見込みがなくなってきたときに、
①工場を売却して得られる金額か②その商品が売れることで回収できる金額の
どちらか高い金額まで工場の資産評価額を下げることになりますが、
この下がった金額は減損損失として特別損失として損益計算書に計上されることになります。
そして②の商品が売れることで回収できる金額の算定にあたり割引現在価値の考え方が採用されています。
たとえば工場を100億円で買っていた場合(本来なら減価償却費を加味しますが説明を簡単にするため無視します)
今工場を売却すれば40億円で売れ、来年まで商品を作れば50億円利益が出るとします。
このとき利率を10%とすると
50億÷110%=約45.4億円
売却額の40億円と比べると商品を作るほうが45.4億円と大きいため
減損処理は
100億円ー45.4億円=約54.6億円
54.6億円を減損損失として損益計算書の特別損失に計上されることになります。
ここで注目していただきたいのは利率を10%としていますが、これは金利とイコールではありません。
ここで用いる利率は金利だけでなく資産に対するリスクなどを加味して決定されるため
単純に金利が下がったからといって利率が変わるとは限りません。
とはいえ金利も加味しますので多少の影響は出てくるはずです。
なお、適用する利率が下がれば将来の収益性も上がるため
(さきほど10%で計算した時は45.4億円ですが、0%で計算すれば50億円となります)
減損しなくてすむという利点が企業に出てきます。
とはいえ利率が下がったため減損しなくて済むという企業は、遅かれ早かれ赤字になる可能性が高いと思いますので
表に出てくるのが遅れる分長期投資にはマイナスの影響があると思います。
-
まとめ
①退職給付債務と②資産除去債務となります
(③の減損処理で用いる割引率には金利以外のリスクも加味しているため直接影響を与えるとは言えないと思います)。
①の退職給付債務はどんな企業であっても従業員がいる限り毎年発生(退職金の積み立て)するものですが、
②の資産除去債務は資産(建物など)を購入しない限り原則新たに発生する性質のものではありません。
このことから金利の変更が企業の財務財務諸表に大きな影響を与えるのは①の退職給付債務となります。
退職給付債務は従業員がいるかぎり退職金を支払う必要があるため
ほぼすべての企業において貸借対照表の負債の金額が変更されることになります。
この変更される金額の影響が大きい企業は先ほど書いた通り
①従業員が多い会社
②貸借対照表に記載されている退職給付債務が多い会社
③高い割引率で計算していた会社
④給料が多い会社
の4つのどれかに当てはまる企業だと思います。
また②の資産除去債務に関しては
株主総会などで大型の資産(工場や建物など)を購入するといった発表があった時に
今までより資産と債務が大きく計上されるため自己資本比率が今までより悪くなることになります。
自己資本比率などの指標を使い、企業の財務的な健全性を評価してトレードしている人にとっては
トレード対象とする株に影響があるかもしれません。
以上のことから金利が変更することによって、今持っているポートフォリオを見直し
①と②から大きな影響がある会社の株を売却し、影響が小さい会社の株を購入する
といったトレードが必要になるかもしれません。
追記 ①
2016年3月9日に退職給付債務の計算においてマイナス金利を使用することに決まったようです。http://www.nikkei.com/article/DGXLZO98231690Z00C16A3DTA000/
↑日経新聞の記事
これで今後金利が下がれば下がるほど支払う予定の退職金より多くの金額を
引当金として負債に計上しなくてはならなくなりました。
追記 ②
日経新聞の記事によりますと退職給付債務に用いる割引率は、主要企業では0.5%から1%で計算しているところが多いそうです。
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO98004500T00C16A3DTA000/
退職給付会計では使用する割引率は
長期国債や安全性が高い(格付けがAA以上など)長期の債券の利率を使用することになっていますが、
マイナス金利の採用により現在-1%から0.3%ぐらいとなっていますので多少影響がありそうです。
ちなみに四季報の2016年新春号で従業員数が多い順にすると7位に東芝(6502)が出てきます。
1万人のリストラをする予定のため財務諸表に与える影響は少なくなるとは思いますが、
東芝にとっては泣きっ面に蜂といったところでしょうね。