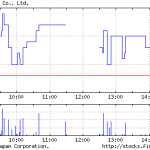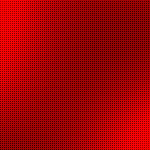引き続きマイナス金利について記載していきます。
③銀行の銀行に与えるマイナス金利の影響について
日本銀行は民間銀行から個人の預金を一定の割合に応じて預かり(準備預金制度と言います。)
その預かった預金の一部に金利を付けて民間銀行に貸し出しています。
そして民間銀行は日本銀行から借りたお金にさらに金利を載せて個人に貸し出しています。
そのため民間の銀行のビジネスモデルは個人へ貸し出すときの金利と
日本銀行からの借り入れるときの金利の差により利益を得ることです(利ざや)。
ちなみに日本銀行に預ける準備預金については金利がありません。
今回マイナス金利の対象となった部分は
今まで準備預金制度を超えた金額を
民間銀行は日本銀行に預けることによって利息を得ていたが、
今後は新たに準備預金制度を超えた金額を預けた金額に対して発生することになる。
今までであれば個人からの預金を預かり、そのまま日本銀行に預ければそれだけで利益が出たところを
マイナス金利が導入されたことにより、今までどおりに個人からの預金を日本銀行に預けると
民間銀行は個人に対しても日本銀行に対しても利息を支払わなければならなくなった。
例を出すと
民間銀行は個人から金利1%で100万円を預かり、日本銀行に金利2%で100万円を預けると
この金利の差額の
100万円×2%(日本銀行より受け取る利息)-100万円×1%(個人に支払う利息)=1万円
1万円が民間銀行の利益となっていた。
次にマイナス金利が導入されたことによりどう変わったかを例を出すと
先ほどと同じく民間銀行は個人から金利1%で100万円を預かり、日本銀行に金利ー2%で100万円預けると
100万円×ー2%(日本銀行に支払う利息)-100万円×1%(個人に支払う利息)=ー3万円
3万円が民間銀行の損失となることになった。
つまりマイナス金利の導入により民間銀行は何もしなければ赤字になる可能性が出てきました。
こうなると民間銀行は赤字になることを避けるため日本銀行にお金を預けることができないので
① 保険などの窓口販売を強化する
② リストラ(合併など含む)をする
③ ATM手数料を上げる
④ 預金金利を下げる
⑤ 運用資産のポートフォリオをリバランスする
といったことが想定されます。
この5つの中でトレードに生かせそうなのは
② リストラ(合併など含む)をする
⑤ 運用資産のポートフォリオをリバランスする
の2つだと思います。
② リストラ(合併など含む)をする
リストラ(従業員を解雇の場合)をしますと基本的に退職金を割り増しで支払うため
一時的に特別損失が発生しますが、来期以降は人件費が下がるため会計上は利益が出やすくなります。
そのため、もしリストラ(従業員の解雇)の発表で大きく株価が下がった場合はチャンスかもしれません。
またリストラ(合併など企業再編)の場合ですが、
合併が発表されると合併することには基本的にメリットがあると考えられるため
株価は上がりやすいです。
そのためあらかじめ合併しそうな民間銀行(地方銀行が良いと思います)を
チェック対象に入れておくことをお勧めします。
⑤ 運用資産のポートフォリオをリバランスする
こちらですがマイナス金利が採用されたことにより国債の利率も同じく下がっています。
そのため民間銀行などの機関投資家が資産運用で得ようとしていた利益目標が達成できなくなる可能性が高まりました。
こういうとき機関投資家はリスク資産の持ち分割割合を増やします。
基本的に国債のようにリスクの少ない資産の持分割合を増やすためREITや格付けの高い社債に
資金が流れ込むことになります。
また株式にも多少は資金が流れることが予想されるため
財務的に健全な時価総額が100億円以上の銘柄が買われることにより株価が上がるかもしれません。
なお時価総額が100億円以上というのは、機関投資家の運用する資金が大きいため
自分の買いや売りの注文で株価が大きく変わるのを避けることと
5%ルールという発行済み株式の5%以上を保有することになった時は
大量保有報告書を提出する義務があるのですが、
これを避けるために時価総額が大きいものを機関投資家は売買してきます。